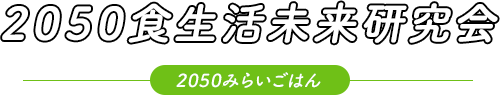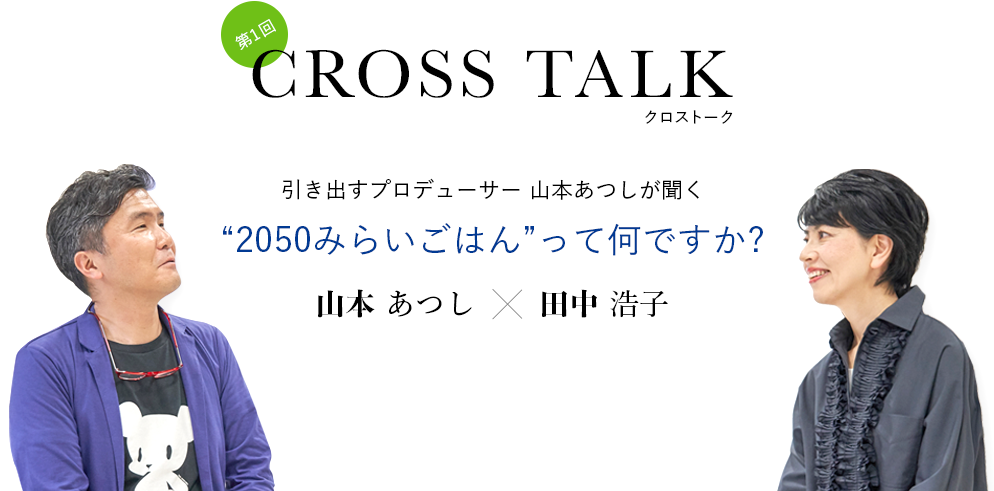“BACK TO 2050” “2050みらいごはん”
-
僕は今、デザインを学ぶ大学で講師をしています。1年生を担当しているのですが、最初の講義で必ずこんな質問をするんです。「あなたはどこから来ましたか?」と。するとほとんどの学生は、「大阪から」とか「島根から」とか「下宿から」とか、ちょっと変わったところでは「お母さんのお腹から」とか、だいたい自分がどの場所から来たのかを答えるんですね。「いや、聞きたいのはそういうことではなくて」と。「みなさんは、ある共通したところから今ここに来ています。さぁ、それはどこでしょう?」と問いかける。
-
えっ?どこ?わからないですねぇ。
-
そう、学生たちも同じように「ポカーン」とするんです。そこで、こう答えます。「みなさんは未来から来ました。」と。さらに、「では、あなたはどんな未来からやって来たのですか?」と聞く。今の自分とは違う自分になりたくてこの大学に来たはず。それならきっと、それぞれに思い描いた「未来像=ビジョン」があるはずでしょう、と。
-
なるほど!おもしろいですね!
-
デザインとは、ビジョンを実現するために計画して実行すること。‘BACK TO THE FUTURE’という映画で、自動車を改造したタイムマシーンが出てきますよね。実はデザインって、未来に戻っていくためのタイムマシーンのようなものなんです。素晴らしい乗り物なのですが行き先がはっきりしなければ、どこにも行けない。これはデザイナーだけではなく、それ以外の人にとっても同じことだと思うんです。ほら、「人生をデザインする」なんて言うでしょう?そこで改めてお伺いしたいのですが、田中さんはどんな未来からここにいらっしゃったのですか?
-
私は…今から約30年後の2050年から来ました。2050年、世界では人口が100億人を突破し、日本の人口は約9500万人と予想されています。85歳になった未来の私は、自分で自分の料理を作っています。食材を歩いていける範囲で手に入れたり、ネットで購入したりしています。そしてこの先、介護施設や病院に入ったとしても、食を楽しめる暮らしがしたいと考えています。
-
2045年には平均寿命が100歳に到達するという予測もありますから、高齢になっても健康で充実した食生活を送りたいと考えている人は多いでしょう。では、そんな未来に戻るために必要なこととは何でしょうか?
-
食材や食事を得る環境を、今よりもっと満足できるものに変えていくことです。また社会保障の側面からも、高齢者の食や食を巡るサービスをさらに充実させることが必要です。


-
そこで立ち上げたのが…
-
《2050食生活未来研究会》通称“2050みらいごはん”です。生活者に対し、人生100年時代をアクティブに生きるための食生活を提案すること。次にそのような食生活を送ることができるように、食環境、すなわち食のインフラを食品流通業や外食・中食産業に提案していくこと。私のまわりにはいろいろな分野の専門家がいますので、ブレーンとして知恵を授けてもらいながら、研究・実践する研究ユニットです。
-
2050年の食生活をより豊かなものにするために、多様な視点から、これからの食環境に新たな提案をしていきたいということですね。
-
85歳の自分の食生活を考えた時、2019年の食環境のままだと困るなと思うようになったんですよね。たとえば、自分で買い物に行き、欲しいものを手に入れて、料理もできる状態であればいいのですが、毎日、毎食、どなたかのお世話になっている状態になったとして、いまも様々なサービスはあります。だけど…ちょっと、いや、うーん、満足しないだろうな…。ちょっと角度を変えて、日常の食生活をベースにしたアクションを起こしたいなと。
-
“2050みらいごはん”のサイト、拝見しましたが、ベースに使っている色が特徴的ですね。普通、食べものに関わるコンテンツには暖色系の色が使われることが多いイメージなので、少し不思議に感じました。
-
「ウルトラ・マリンブルー」という、私の好きな色なんです。
-
なるほど!海は生命の起源と言われますし、そこから「食」の未来を作っていくという意味で、“2050みらいごはん”にぴったりな色ですね。


昭和、平成、そして令和の食生活を考える
-
第二次世界大戦中、戦後は食糧が不足し、栄養状態が非常に悪かった時代です。そんな状態から抜け出すために、国民みんな、そして国も民間企業も頑張った。そして昭和50年(1975年)ごろ「日本型食生活」が完成します。
-
ごはんに味噌汁、主菜、小鉢があって…という食事ですね。
-
そう!主菜に、ハンバーグのような洋食や酢豚・八宝菜のような中国料理も登場し、献立の幅が広がってきました。世界からも絶賛されるものだったんですよ。当時は、専業主婦が多く、食材や料理の情報も増えてきた時代。今まで見たことがなかったような献立提案も、テレビの料理番組で盛んに行われていました。


-
「昭和の食卓」が思い浮かびますね。それに比べて、30年間続いた平成はどんな感じだったのでしょうか?みんながイメージできる食のシーンが、パッとは思い浮かばないのですが。
-
平成時代は、健康に敏感になった時代。「塩分を減らしましょう」「脂肪分を控えめにした食生活を」と、提唱されているんですけど、生活習慣病は全然減っていないんです。むしろ増えているんですよ。寿命が長くなっているし、運動量が減っているのも原因のひとつだと言われているのですが…。もうひとつ、昭和と違う点として言われているのが、生活習慣が大きく変化していること。外食に加えて、百貨店やスーパーマーケットでの中食の質が大幅に向上しましたし、また職場や住いの近くにコンビニエンスストアがあり、日常の食事がすぐに手に入れられるようになったのが平成時代。暮らし方も食生活もバラエティ豊かになった時代なんです。
-
食の価値観も多様化していったのですね。
-
食に対するお金や時間のかけ方も本当に多種多様、そんな中で、「“2050みらいごはん”のユニットはこう考えます」という食提案をしていくつもりです。料理を自分で作るのが苦手な人、作るのにあまり時間はかけたくないけれども、栄養のバランスがよい食事をきちんと摂りたい人向けの提案、というようにバックグラウンドに合わせた提案をしたい。令和時代を生きる人の提案にしたいですね。
-
‘欲しいと思う人にきちんと届く’、まさにマーケティング的な提案ですね。それでひとつ思い出したことがあります。知人の小学生の娘さんの話なのですが、たまに料理レシピ動画を見ながら夕食を作ってくれるそうなんです。‘小学生がひとりで作る’、‘料理’、‘簡単’などのワードで検索すれば、子どもでも欲しい情報をすぐに手に入れられる。それは、SNSなどの発達によって、一般の人でも情報を気軽に発信できるようになったことが大きいのではと。ここ20年余りの間に、誰もがメディアになれる時代が実現したわけです。
-
そうですね。専門家が提案するだけではなく、いろんな方向からの提案や意見があっていいと思います。それがこれからのやり方。“2050みらいごはん”は、そういう新しい枠組みで行動することをめざしているんです。
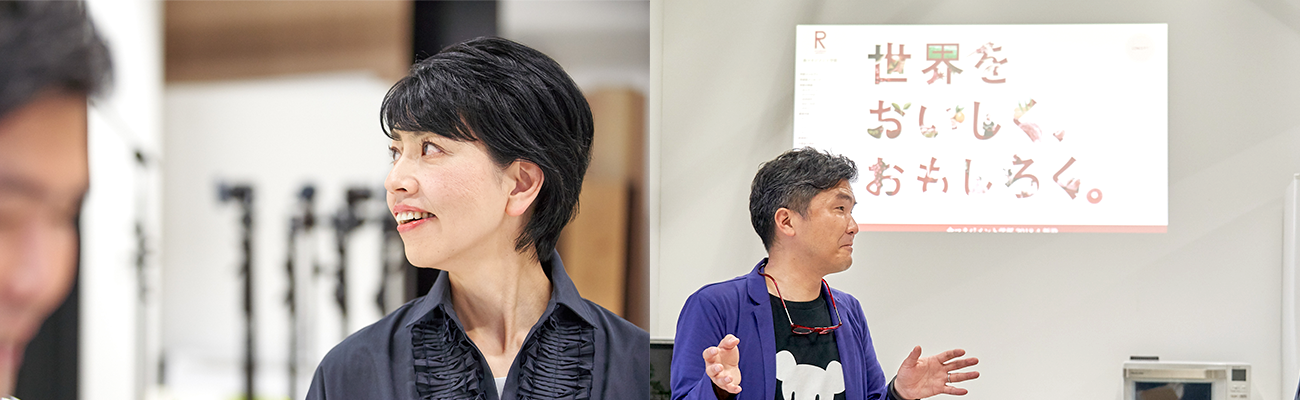

さまざまな視点から食へアプローチ
-
田中さんは、僕の母校でもある立命館大学で教えられているんですよね?
-
はいっ!立命館大学の食マネジメント学部で流通論やマーケティングを担当しています。
-
ホームページを拝見しましたが、学部のコンセプト『世界をおいしく、おもしろく。』って、なんだかワクワクしますね。
-
2018年に創設された日本で初めての食を総合的に学べる学部なんですよ。生活や健康といった身近なことから、政治、経済、外交、環境、エネルギー、格差といった社会問題にも関わってくる。経済学・経営学マネジメント(社会科学)を基盤としながら、カルチャー(人文科学)やテクノロジー(自然科学)の3つの領域から総合的に学んで、考える力を養おうというのがこの学部なんです。
-
教員陣もバラエティ豊かな方が揃っていそうですね?
-
ええ。経済、マーケティング、食文化、歴史、心理学、環境などバラエティ豊か。多種多様な視点で食について議論できるので、今まで行われていなかったアプローチをできると期待しているんです。学生も、食に関して興味津々で入ってきた子たちばかりで意欲的です。

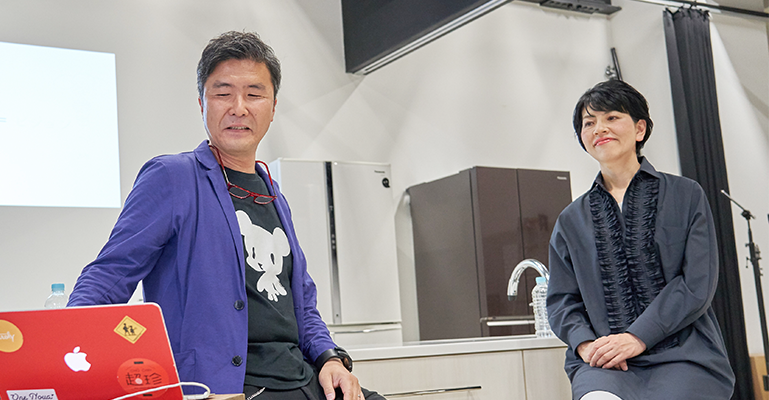
食から見えるまちの課題、まちの未来
-
キャンパスは滋賀県草津市でしたっけ?
-
ええ。そのご縁で、草津市と協力して、食を切り口としたまちづくりをしようとしています。
-
いわゆる、地域連携というものですね。
-
はい。草津市は人口増加エリアと減少エリアがあるんです。3世代同居も、他の地域に比べて多い。データとして出てきているものはあるけれど、実際にはどんな食生活になっているのだろうか?地域に入って、話を聞かないとわからないこともたくさんあるので、住民にインタビューして、食に関して、何を求めているか?何が問題か?などを浮き彫りにして、地域再生計画の足がかりにするつもりです。
-
僕もまちづくりの事業に関わることが多いので、自分の足で歩いて、人に話を聞くことの大切さはよくわかります。地域に飛び込んでみることで、客観的データでは見えなかったことが見えてくる。
-
そうなんですよ。「このエリアとこのエリアに、コンビニがあればいいよね」じゃない。ミニスーパーが必要な地域もあれば、高齢者が多いから巡回販売が喜ばれるエリアもある。お買いものの仕組みをちゃんと考えて提案するのが大事なんですよ。さらにもうひとつ課題があって。
-
何ですか?
-
草津市の湖岸は農業地域なので、作っている野菜は多いんですね。しかし、市民の野菜消費量は少ない。それならば、どこでどう売ったら市民に届くのか、を考えなくちゃいけない。
-
地元で採れた野菜が市外で売れるのは、経済的にはいいのかもしれないけど、長い目で市民の食生活のことを考えると疑問ですね。もう少し ‘地産地消’志向になってもいいのかもしれない。


集い、つながる食の場づくり
-
もうひとつ、地域の食生活を考える中で、「公」の役割も考えていきたい。食の「公」というと、保健所・保健センターを通じての活動があります。
-
保健所ですか?一般の人からすると、どんなことをしているところなのかわかりにくいかもしれませんね。
-
母子保健、予防、健康づくりなどが主な仕事です。飲食店や喫茶店など食品に関わる店を開業するときの許可なども。地域住民にとっては重要な仕事なんですよ。これから人口減少にあわせて、まちをダウンサイジングしていく必要があります。その時に、従来の「公」の役割に加え、日常の食生活の質を保つ、向上させるしくみを整えていくことも必要だと考えています。例えば、買い物にいく交通手段や公的な施設の活用方法についての情報提供とか。
-
なるほど、時代を先取りした施策が必要ということですね。一方で今、「シビックプライド」という言葉が注目されています。これは「まちに対する愛着や誇り」という意味なのですが、行政任せではなく、市民が自発的にまちの課題解決に取り組んでいく姿勢のことでもあるんです。以前、あるまちの社会福祉協議会から、高齢化が進む古い団地の中にある幼稚園を、地域の人が集う場所にリノベーションしたいという依頼をいただいたときのこと。そこで考えたコンセプトは、'DIY(=Do It Yourself)'でした。ペンキを塗ったり、家具を作ったりという一つひとつのプロセスをイベントにしたんです。
-
自分たちの場所を自分たち自身で作るって、なんだかワクワクしますね。
-
地域に住む人に加えて、SNSなどで情報を知り、集まった地域外の若い層の人たちも一緒になって、楽しみながら場づくりに参加してくれました。そして完成する頃にはいくつかの自発的なコミュニティが生まれ、今ではいろんなレイヤーの人たちが集まるようになりました。小さな厨房もあるので、みんなで集まってごはんを食べたり、まるで‘まちの中の茶の間’のような空間になっています。
-
いいですね。「食」を通して、人と人とが繋がっていく。
-
ふと、‘コミュニティ’と同じ語源で‘コミュニオン’という言葉を思い出しました。キリスト教における「聖餐」、つまり最後の晩餐を再現して、みんなでパンとワインを分け合う会食のことなのだそうです。
-
‘同じ釜の飯を食う’ってことですね。一人ひとりの幸せは異なるでしょうけど、食を通して公共政策に関わることで、 ‘幸せとは何か’をみんなで考えていきたい。これからの時代にフィットする案を草津市と一緒に、‘びわこくさつモデル’と言われるようなものに仕上げたいと思っています。


『静かな食育』
-
「自発的」というワードが出てきましたが、管理栄養士のお仕事をされていた時に、人間の習性を上手く利用した食べ方提案をされたとか。
-
『静かな食育』と名付けた、ある社員食堂での提案ですね。これは、後でわかったのですが、仕掛けを作るという意味の英語=Nudge(ナッジ)が根底の考え方にあるんです。
-
ナッジ?
-
経済学者リチャード・セイラー博士が提唱した行動経済学の概念で、強制的に何かをさせるのではなく、人々を自発的に望ましい方向に誘導する仕掛けや手法のことなんです。健康を促す食提案って、「〇〇してはいけません」が多いでしょう。でも、それでは食事が楽しくないなぁと思って、思わず食べてしまう、という環境作りです。
-
具体的にはどんなことをされたのですか?
-
副菜の提供方法を変えたり組み合わせを促すような定食を提供しました。たとえば、「野菜盛り放題」を組み込んだ定食…これは元々給食会社の社長のアイデアなのですが。サラダバーから、好きなだけ野菜を盛っていい。「おかわりなしで、1回盛り切り」というルールで。すると、お皿にいかにたくさん盛ることができるか…みんな真剣なんです。「野菜を食べましょう!」というよりも、グラム計量のサラダバーのときの1.5倍くらいの野菜を摂ってもらえる!
-
「こうするべき」「これはやってはいけない」と言うのではなく、自発的にやりたくなるように仕向けるというわけですね。
-
そうです。社員食堂だと社員限定になるので、次は誰でも食べられる場所でこの仕掛けを使った食提案をしてみたいですね。


みんなで考えて、これからの食生活を作る、それが“みらいごはん”
-
『静かな食育』が成功した要因は何だったのでしょう?
-
私は、病院や食堂などで管理栄養士として働いたことがありません。つまり、食を提供する立場になった経験がないんです。提供する立場、受け取る立場、どちらかというと、受け取る立場で考えたのが良かったと思いますね。
-
提供する立場と受け取る立場では、論理も視点も違いますからね。
-
私が学んだ昭和終わりの栄養学では、提供側から見たマネジメントの概念しかありませんでした。
受け取る側の視点が必要だと気付いたのは、起業したあとに通った、中之島に本校があった辻学園のフードビジネススクールでマーケティングを勉強してから。ものごとをいろんな立場から見る大切さを知って、仕事でも食べる人の視点で考えるようになりました。 -
デザイン思考においても、人間中心の思想が原則であるとされています。しかし現実は、まだまだプロダクト・アウト重視の考え方が根強い。企業も、行政でさえそうであると感じます。相手の立場に立って思いやる視点が欠けていますよね。
-
でも、これからの時代は、両方の視点を持つ人が必要とされるはずだし、いろんな方向から多彩な声が出てくるはず。“2050みらいごはん”が提供する立場と受け取る立場のギャップを埋めていけたら、と考えています。
-
ダイバーシティ&インクルージョンの時代、どんな立場であれ、ものごとをよく観察し、想像し、対話する力がさらに問われるようになると感じます。
-
みんなで参加して、みんなで考えて、みんなで新しい食提案をする、そんなコミュニケーションの場に“2050みらいごはん”がなればいいと思っています。

山本 あつしやまもと あつし
ならそら代表。大阪芸術大学 デザイン学科講師。奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略懇話会委員。1971年大阪市生まれ。1993年立命館大学、1999年大阪工業大学卒業。システムエンジニア、建築設計・施工の仕事を経て、「デザインの考え方で社会をおもしろくする」をテーマに、商店街や農村の活性化、企業・店舗のブランディング、商品開発から学校づくりまであらゆるプロデュースを行っている。
ならそらnarasora.amebaownd.comライター:宮前晶子
撮影:田口 剛
ヘアメイク:石田 咲苗