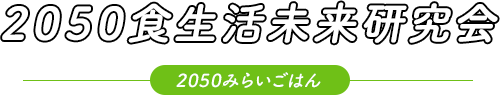諸国漫遊で、農業に出会う
-
もともとはジャーナリスト志望?
-
幼少時、福岡から東京に越して当時の公害病「環七ぜんそく」になりました。それでも外に出て土や花や虫に触れることが好きでした。両親はそれを見て、なるべく好きなことをさせて、自然の力で治すこともできるんだと滝に連れていってくれたりしました。病気を克服するのではなく、寄り添うことを教えられたと思います。ちょうどその頃は開発でサンゴ礁が失われるなどの環境問題が出はじめた頃で、自然がコンクリートで閉じられていくことの息苦しさを、自分となぞらえて痛々しく感じていました。息ができない!みたいに。自然を克服する、征服するような開発のあり方に、疑問を感じていました。小学校のどじょうすくい大会も嫌いでした。一匹を手のひらに捕まえて、どうやって川に戻してあげようかと考えているような子どもでしたね。そんな理由から環境ジャーナリストを志望して、そういう大学へ入りました。
-
20代は諸国漫遊の時代ですよね?
-
はい。イタリアの修道院に泊まったときは宿代代わりに、朝4時ぐらいから起きて農業をお手伝いしまして。それが最初に触れた農業。諸国漫遊と農業のきっかけがそこなんです。
-
そこからいきなり商社に入っちゃう。
-
まさに漫遊の成果なのか、ジャーナリズムという枠組をとって一番したいことを考えたら、衣食住の仕事をしようと変わっていったんです。当時はまだ中途半端で、映像や音楽で伝えることができないかと思い、環境保護団体や環境フィルムを作る映画会社に入りたいと考えていました。でも、経験がないとダメなことが多く。そんなとき母が「環境の開発者である商社に入って、本当の最前線を見たらどう?」って。「なるほど!取材ができる!」と、そこでまたジャーナリズムの枠組みが出てきたりして…、商社の扉をたたきました。
-
配属されたのが…LNG(リキファイドナチュラルガス)、液化天然ガスですね。
-
当時は最先端のエコ・エネルギーと言われていました。日本経済も多大なコストを払って天然ガスを現地と共に開発し、輸入していたんです。液化天然ガスを詰め込んだ東京駅ぐらいの大きなLNG船の就航を見届ける仕事に実に多くの人が関わっていること、エネルギーの恩恵と開発の規模を目の当たりにしました。当時のチームリーダやチームのみなさんは仕事をすることの現実を教えてくださった大事なメンターです。電気が当たり前のように手に入る東京にいて、いかに無意識に恩恵に浴していたかと知りましたし、物事の価値はそう簡単には決められない、自分はもっと勉強しようと素直に思いましたね。


トップデザイナーのもとで、衣の仕事
-
そこから、ファッション業界に進んだんですよね?
-
はい。とある大学院の授業で「イッセイミヤケのデザインとものづくり」に触れました。先生の講義は言葉がシンプルでユニークでした。次は「衣」から環境を考えようと思いました。文化事業やウェブの構築、さまざまなアーティストとのコラボレーションの末端に関わらせていただきましたが、「一枚の布」というコンセプトはなんて根源的で本質的だろうと思います。イッセイ・ミヤケデザイン スタジオでは、早い時期から衣服作りと環境のありようを考えていました。リサイクル、リユーズは、当時からテーマでした。ただそこで大事なのは、ただエコを取り入れるのではなく、本来の服づくりの原点に立ち戻ることでした。衣服をファッションではなくデザイとして捉え、デザインを通し社会へ関わりることができるのだと思いました。フード・ロスの問題がこれだけ大きくなってきましたが、服作りにもまだ知られていない生産背景があります。
-
バブルのちょっと後は、まだそういう意識がなくて、デザイン重視。今は、環境を考えた服づくりを意識している人も多いし、そういうブランドも増えているけど。早い考えですよね。
-
クローズシステムをオープンにしていくこと、既成の枠にとらわれず、自由な発想をしていくための先端のリサーチとプロトタイプづくり(実証検証)を経ること、何のためのデザインなのか?という姿勢がはっきりしていました。素材の持つ力とその実用の美のなかには、自ずと環境と調和する伝統の技があり、それと最先端技術を共存させて時代が求める[Making Thnings](ものづくり)をすること、その魅力に傾倒しました。
ファッションの世界から農業へ
-
そこから農業にいくんですね。
-
最近では、カンボジア絣を再生するために生態系復元した森本喜久雄さんとの出会いが大きかったですね。森本さんは西陣の職人さんだったんですけど、カンボジアの地雷の埋まっている地域で森づくりをして、桑を作っていったんです。そして、内戦で打ち捨てられた機織り機を修復し、おばあちゃんたちの手に遺る機織りの記憶から、カンボジアシルクを再生しました。
-
わぁ、すごい…
-
その様子を知って、もっともっと人と自然の関係、その復元と創造の現場に近づいていこう、という気持ちが高まりました。だから、イッセイミヤケから農業への転身っていうのは、私にとってはすごく自然な流れ。
-
服も食も、もとをたどれば同じっていう感じ?
-
そうですね、衣食同源。イッセイ・ミヤケでの服づくりには、いろんなストーリーがありましたが、農業にも無数に生態系の代弁者のような語り部がストーリーを編んでいます。まだまだ知られていない食べものの語りがあるはずだから、それを研究したい、と思ったんです。


農業文化人類学を追求して
-
私の農業のきっかけは、水や肥料を極力控える、野菜の持つ力を最大限引き出すという永田農法を提唱した永田照喜治先生なんですけど、生産される農産物は、まさにアートでした。永田先生は農業ではなく、農芸を担う人材を発掘しては、各地でイノベーティブな農芸を普及しました。永田先生に「農芸を本気で学問にしたらいいんです」とおっしゃっていただきました。社会人から大学院に入り、農業と環境を学び直して、博士を取得した後、早稲田大学の指導教官、原剛先生と山形県高畠町で早稲田環境塾のフィールド学を展開していたときに、長年高畠と生きた関係をつくってこられた立教大学の栗原彬名誉教授とお会いしました。栗原先生は、アートはもちろんマンガ、演劇などの文化、そして社会学、政治学、ジェンダー、「やさしさ」など多くの切り口で社会を捉える研究者で、高畠町とは深い関係を構築されていました。そこで「吉川さんの研究は農業文化人類学にはなりませんか?そう名乗りませんか?」お声をかけて頂いたのです。衣食住から考える農の価値、頭を打たれたような瞬間でした。文化人類学をベースにした農業社会学、環境学、経営学は究極のアートで、それを誰とどうデザインし、何を創出していくのか?扉が開いたような瞬間でした。そこからは農業文化人類学の路を自分で仲間をつくりながら進めばよいと定まりました。
-
大学院で勉強しながら、キューバや中国に行ったり。そこで学んだことで、大きかったことってあります?
-
日本の経済発展・近代化って何だったのかなと考えるんですよね。食に関して、生産者と消費者が分断されてきちゃった、とすごく思うんです。中国では、日本のメーカーや商社が介在する野菜の生産現場を見ましたが、日本の市場が決める規格、重さ、色、見た目を揃えたものを出荷するんです。ネギは青い部分をカットして、長さを揃えて、サトイモは丸い球体に。遠い中国で日本の市場が要求する形に揃える仕事をしている女性たちがいます。国外のみならず、日本でも。ゴボウも今、丸ごと売ってる姿はなくなってきています。
-
ちゃんと2つに折って、25センチぐらいで均一。
-
泥付いてないですよね、まな板のサイズに合わせてるし。規格化された農産物っていうものが、日本では当たり前のようになってるんです。でも、そういうものは中国の一般家庭のテーブルには乗らない。キューバもそうなんです。全然規格化されてないんですよ。そういうのが非常に面白いな、豊かだな、と感じました。
-
たかはた共生プロジェクトはちょうど一緒ぐらいの時期?
-
そうですね。有機農業運動が盛んだった山形県高畠町で生産者と消費者が直接つながる“提携”という形で震災後、分断された都市と農村の共生を目指して始めました。
-
“提携”、キーワードですよね。
-
かつて、日本では、空中から人が暮らしに近い水田に農薬を降り蒔いていた時代がありました。空中からの農薬散布写真を授業で見せると、「中国のことですか?」と言われたりもするんですけど、実際に農薬を被っていなくなった小さな生き物や病気になってしまったり、亡くなったりした農家の方などもいました。そういう経緯を経て、安全安心で技術も安定した日本の農業になったわけで。安全で安心な食を求めて、農家と消費者がつながろう、と始まった提携に、私は今後の農業の活路を見出したような気がしたんですよ。
-
生産の裏側を知るってことですよね?
-
そうなんです。農家の生き方や苦労、そして歓びをみんなが共有して、食べ物を分かち合って、つながりが生まれるんですよ。そういう状況を目の当たりにして、「ああ、これからの農業では、こういう関係価値みたいなものが広がっていくんじゃないかな」と感じました。


これからの農業のゆくえ
-
これからどうなるんだろう?と不安を抱えるよりも、こうあって欲しい、ということで、何らかの手を打っていきたい。それで、この研究会を始めたんだけど、私は生活者と、食品小売業、外食・中食産業、そして食品卸売業あたりまでを主に見ています。生産者の立場で見る機会はどちらかと言うと少ないので、ディスカッションしたいなと。2050年の食にどんな予想をしています?
-
消費者 が何を食べてどう生きるか、でしょうね。これ、食料主権と言われているんですけど…。食料主権がどう保たれるかによって、各国が保有して持続する農業の姿が随分異なってくると思うんですね。日本から始まった“提携”は、英語圏ではCSA(コミュニティ・サポーテッド・アグリカルチャー)と呼ばれて、海外で盛んになっています。自分が何を食べてどう生きるかについて、鋭く強い意識を持つ消費者がいて、信頼のおける農家と提携し、農家の生活全体を支えます。農家はただ農産物を生産するという従来のあり方を超えて、「食」をプロデュースする側に回っていくイメージです。これからは、農家+栄養士、農家+健康アドバイザー、農家+ボディトレーナーなどの「機能としての食」の連携、または流通や小売り現場との一体化がますます進化した「システムとしての農の連携」が増えていき、農業を変えていくと考えています。かかりつけの医者がいるように、「フード・ライフタイルパートナー」として個別の消費者に関わっていくのではないか、と。2050年の農家のスタイルは大きく変わるでしょう。
-
そうなんですね。
-
日本社会の今後を考えるなら、私たちが何を食べてどう生きるかをもっと意識的に考えないといけない。今は当たり前のようにある、安全で安心で、高付加価値で、質の高い農産物が価格競争で負けて、生産者もどんどん少なくなってしまうかもしれない。私たちの世代で食い止めるような策をしなければ、と思うんですね。
-
価格競争に負けて生産現場が減るということも考えられるけど、どんどん人が減っていくと生産はどうなるんだろう、とも思っていて、そこはどう考えていますか?
-
1970年の日本には農業に従事している人が1025万人いました。それが年間10万人ベースで離農が続いていて、2015年の統計では239万人。そのうち、75%は60歳以上の高齢者なんです。永田先生はこれまでの生産農家が減っても、一人あたりの耕作面積が増えたり、農業生産効率が高まるので農業人口の減少には、あまり心配していませんでした。むしろて農業に適したスマート化を図り、生産だけではなく、それこそものづくりに関わる別のサービスが生まれ、老若男女、多様な人材、全ての人が農業に関われるように変革するチャンスだとも言っていました。世界でも大農場があると思いきや、変わらないのは家族経営が多様に続いていくことです。
-
家族単位でやってるってこと?
-
そう。でも、農業生産法人として、経営してもいいんですよ。大事なのは農家のアントレプレナーシップです。別の仕事との違いは、自然、生き物相手のものづくりに、個人個人のこだわりや個性が発揮され、自らが主体的に関わる家族経営の形です。今まで無駄の多かった部分にITを活用してもいいと思う。その方が無駄が出なかったり、環境にいいこともいっぱいあると思うし、コストもセーブできる部分もある。どういうスマート化を進めるかは、どういう農業を残していくか、ということにちょっと似ていると思うんですよね。農業生産は、ある意味、効率化が進んでくるので、従来の農業とはイメージが異なる形に変化しながら、農業人口が減っても…
-
守られていく?
-
はい。ちゃんと生産されたものが、何一つ残らず選ばれて、求められるような社会にしなくてはいけない。統計的に見ると、世界の農業の約73%が1ha未満の小規模農業です。小規模・家族農業は、世界の農家の9割を占め、食料の8割を生産しています。海外では労働人口の変化、生物多様性の保全、気候変動への適応策としても家族農業の支援が政策的に行なわれています。それが安全保障にもつながっているんですよ。食料問題は要になると思います。食や農業に対してダメージを与えるような生産活動をしても誰もいいことがない、という意味で、食自体の原点に戻りつつある、と感じています。国連でも今年から10年間は、家族農業年となっています。
-
それは、知らなかったですねぇ。
-
多様性のある社会を担うのは食だ、と各国合意したんです。食の有り方はまさに文化です。固有の文化を守るという意味もあると思います。


食は、地域で行なうSDGsの要になる
-
永田先生は、「農業は人類が手にした最初の芸術で、農業は自然破壊の始まりだ」とおっしゃっていて、自然に遠慮しながら農業をやっている、という考えでした。それって、SDGsやエシカルな消費にもつながっていると思うんですよね。
-
SDGs、サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズですね。
-
当初、サスティナブル・ディベロプメント(SD)が提唱されたとき、まだ開発・経済発展VS環境保全という構図がありました。しかし、現在は環境保全しなければ開発・経済発展はないというところまで変わってきました。プラスティク問題も急激に変化しています。ゴールを設定して、みんなで一致してそこまで何か動きをつけよう、と。でも、実際はゴールのない話で…。
-
ないですね、続いていくと思う。
-
サスティナビリティの“サス”は、宙ぶらりんという意味なんです。“ティナビリティ”は、安定化する。宙ぶらりんのものを安定化させるということがサスティナビリティなんですけど。私、「食」っていう漢字は、サステナビリティやSDGsの本質を表現しているなと思っているんですよ。
-
えっ?なになに?


-
この上の部分、屋根のように見えるでしょう。これは、絵としてみるとひとつの家みたいだなぁって。または傘。両サイドは、生産者と消費者、山と海、里と川、または発展と保全、自然と人間などで、この両サイドのバランスを「良」という倫理的な有り方で支えている。二つの方向のどっちかが偉いとか、正しいというような主観やエゴではなくて、お互いに支えて、相対的なもの。それを安定化させるのが「食」なんではないかと。
-
あっ!ホントだ!
-
自然にどういうフィードバックをするのか。食べものを得て、消化をして、ちゃんと土に還るゴミを消費していく。生きものと自然の全体の関わりの中で、食が存在しているんです。善良な循環、食物連鎖ですよね。
-
なるほどね。生きものと自然の全体の中に食があるとして、では、地域で実際にSDGsの17項目を行なうとしたら、どうやっていったらいいんですかね?
-
ものごとを両サイドから観ることでしょうか。そして、人が生きている場所はやはり地球ですよね。日本には身土不二という言葉があるでしょう。体と土は二つにならない。つまり一つである。人が土をつくり、土が自分を作ってくれる、人間は環境に似ていくという発想なんですね。自分がどういう暮らしをするかで、自分に返ってくる。人間が自然や経済活動にどう介入するかで、またそのツケが人間に回ってくるんですよ。食物連鎖みたいなものですよね。だから、その食物連鎖を自分の身の回りで、ひとつずつやっていくことがSDGsの解決に近づくのではないかな、と思うのですが。
-
できることから少しずつ、ですね。
-
国連は、常に貧困削減を目指していますが、飢餓は、今でも解決できていない。食は最大の欲望です。欲望の質を高める必要があります。
-
そうですよね。
-
一方で先進国の貧困もあって、子どもたちの栄養の問題もあります。支え合って生きるというスタイルが分断されているのが、今の日本だと思うんです。地域でSDGsをするには、食を伝えるためのコミュニケーションを増やしていくことも考えていかなくてはいけない。生産者と消費者を分断させない生き方をどうしたらできるのか?それが、農と食の醍醐味でもあるし、これから先も失われない価値なんじゃないかな。


まだまだわからない食、でも尊さは変わらない
-
食って未だにわからないことがいっぱいあって。私が小さい頃って、食物繊維は「食べ物のカス」すなわち要らないものという認識だったけど、食べものの中に入ってるから、それを知らず知らずに取り込んでいた。
-
はーん。
-
「食べ物のカス」が、ある時から、すごく体に有効である、とわかってきた。そして「食物繊維」と呼ばれるようになった。それと同じように、今も食べものには、まだまだ分からないことがあると思うんですよ。まだ解明されていない効果があったりするので、やっぱりサプリメントよりも食品から取るのが一番かなと。
-
土も、まだ分からないことだらけですよ。土の中の栄養素は、私たちの体の中で循環しているんですよ。だから、土に還るという生き方をすることも、これからの食のテーマにあると私は思ってます。 熟練農家は土を触った時に、観察してるんですね。いろんな菌や栄養素がどのくらい育っているかって。英語で農業のことをアグリカルチャーと言いますが、“カルチャー(日本語で文化の意味)”は耕すという意味のラテン語に由来しています。そこから、心を耕すということで、文化という意味になったんですよ。今後は、農業を残そうと思ってやることよりも、食べものの楽しみを知るってことが非常に伸びてくる傾向なんじゃないかなと思ってるんです。農家の人が一生懸命作った稲を、稲刈りに参加して、天日で干して、それを実際にいただいてね。ご飯をお釜で炊いて、おむすびを海苔でパッと巻いて食べる喜びっていうのは、かけがえがないでしょう。すごく嬉しいっていうか、悲しいっていうか。心に刺さるんです。
-
あぁ、わかる気がします。
-
『千と千尋の神隠し』という映画で、千尋があの世に近いところに入っちゃう場面、憶えてます?異界に入ってしまって、だんだん透明になっていく千尋にハクが丸い赤い粒をたべさせて透明ではなくなるのだけれど、そのあとに豚になったお父さんとお母さんを見て元気がなくなっちゃうんですよね。今度はハクが、おむすびを食べさせてくれるんですよ。そのおむすびを食べた時に、人間の体としての元気がヒューって戻ってきて、わーって泣くシーン があるんですけど。あれ、人間を取り戻す瞬間っていうか、おいしさのノスタルジーっていうか、感動なんだと思うんですよね。悲しいような、嬉しいような、命をいただいてるっていう気持ちとか、自分の命がこれで蘇るっていう気持ちとか、生きている喜びみたいな。そういうことに、もっともっと近づいていくんじゃないかな。
-
すごくシンプルですよね。
-
そうなんですよ。なんてことないものじゃないですか。だけど、それが、やっぱりこう、ああ、命を繋いだ、って気持ちになる。


近江商人の三方よしは、SDGsに通じる
-
立命館大学食マネジメント学部のキャンパスがある滋賀県と言えば、近江商人でしょう。「売り手よし、買い手よし、世間によし」というあの考え方は、SDGsに近いんじゃないかと思っていて。あそこにプラスアルファ、たとえば、もっと将来や将来の世間についての視点があれば、SDGsにつながっていくんじゃないか、と。
-
未来ばかりを見据えるより、自分たちの土地の記憶や空間の履歴、そういう先祖からいただいたものを、継承していく、過去のステークホルダーを入れるということが、今後の、アジア発のSDGsになってくるんじゃないかと考えています。国連主導のSDGsの考え方は、3世代先なのか、4世代先なのか、みたいな話があるんですけど、今こそ、次の世代だけじゃなくて、実は過去の記憶、育ててくれた人、見えない命のつながりも見ないといけない。命は巡るという自然観が根底にあるかないか。文化の根底にある自然観が異なる。
-
なるほど。ところで、私には、地域の中で循環型社会が見えた方がいいんじゃない?っていう発想がなかったんですね。それは、どういうことなんでしょう?
-
地域循環については、廃棄物の循環がわかりやすいですよね。自分たちの出したゴミはどこに行くのか?流した水はどこに行くのか?もう次の瞬間には忘れているし、どうなっていくのか知らないと思うんです。どこへ行くのかっていうつながりを考えない社会になってきているんですよね。だけど、それこそ近江商人が生きていた少し前の時代の日本では、自分たちが出したゴミや堆肥を限りなく利用していたでしょう。
-
江戸ってそうですよね。江戸が一番、循環型社会として成熟していた、と。
-
気候変動や災害や突然の食糧危機にも備えていたんでしょうね。そういう社会を維持するには、やっぱり地域循環をするべきなんですよ。衣食住全てがつながっている社会を、小さくてもいいから実現していく。その小ささが地域だと思うんですよ。


生産者と消費者が支え合う提携
-
地産地消もこの頃言われているでしょう。でも、地産地消で収まってしまうと、経済的発展にならないんじゃない?という疑問もあって。他に売っていくために作るから経済的発展があるんじゃないかと思うんだけど、そこはどう考えていったらいいんですかね?
-
鮮度のいいものを食べているから地産地消ということではないと思うんですよ。作られた背景を共有することが地産地消。地産地消の「ち」、は知識の「ち」、「知産地消」と言う方もいるんですが、大いに賛成します。農家や漁師がどうやってここで収穫したのか、そういう情報が届く範囲に、農産物は旅をしていく運命にあると思うんですよ。
-
あぁ、“提携”ってそうよね。わかってる、っていうこと。
-
「わかってくれる」という存在があること、これは現在、何にもかけがえのない安定感や、許容度の高い関係を生みます。提携にも、いろんな提携があって、公共交通期間で行く範囲にすべきだとか、フードマイレージや流通コストの問題で議論があります。でも私たちの食生活はそのおかげで実現できている部分が多々あります。だけど、コストや人手不足で、同じような便利さが実現できない、さぁ、どうする?って時代になりつつあるんです。
-
なるほど。
-
ラオスのコーヒー農家と“提携”してる京都の八百屋さんがあるんですね。あえて八百屋さんと言っているんですけれど、“提携”は今、国を超える時代になってきています。誰がどういうふうに作ったか、知った上で買いませんか?という形。
-
2050年は、自分がわかって食べるということが大事ですよね。
-
農家と消費者は何回も分断されてきたけど、つなぎ直して。中間に入る人がもっともっと増えてきたらいいんじゃないかなぁ、っていうふうに思います。もっと言えば、この中間が大事ですし、これまでのフードチェーンはより個別のバリューに従って、質を深めていくのだと思います。
-
つないでいく人ですね。
-
どんな農家を支えたいか、でしょうし、逆もある。実際に提携をやってると、消費者の方が支えられることが多いんです。それが海を超えて、遠くのラオスのコーヒー農家で、1日1ドルぐらいで暮らしている人たちかもしれない。国連の貧困水準を下回るたちかもしれないんですよ。そういう人たちとつながることが、平和的な食の分配だと思うんです。
-
分配。分かち合い?
-
そう!それこそ、「食」の原点ですね。どっちかがワガママを言ってる関係じゃなくてどっちともイーブンで良し。どちらかに傾いても、失敗しても、そのバランスで修正していける関係が大事。これ、サスティナビリティって言ってるようなもんですよ。 2050年の未来は農業が「食」をめぐる社会的な許容度を受け入れていくサードプレイスになることを願っています。



吉川成美
県立広島大学大学院経営管理研究科 准教授。上智大学文学部新聞学科卒業。東京農業大学大学院農学研究科博士後期課程 修了。専門分野は農業と持続可能な地域ビジネス、自然資源管理、CSA(Community Supported Agriculture)と食料システム構築。早稲田大学HNRM研究所主任研究員。URGENIC理事。たかはた共生プロジェクト副代表。
ライター:宮前晶子
撮影:アスコン
ヘアメイク:CAPA Justhair