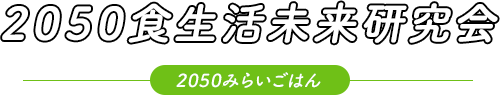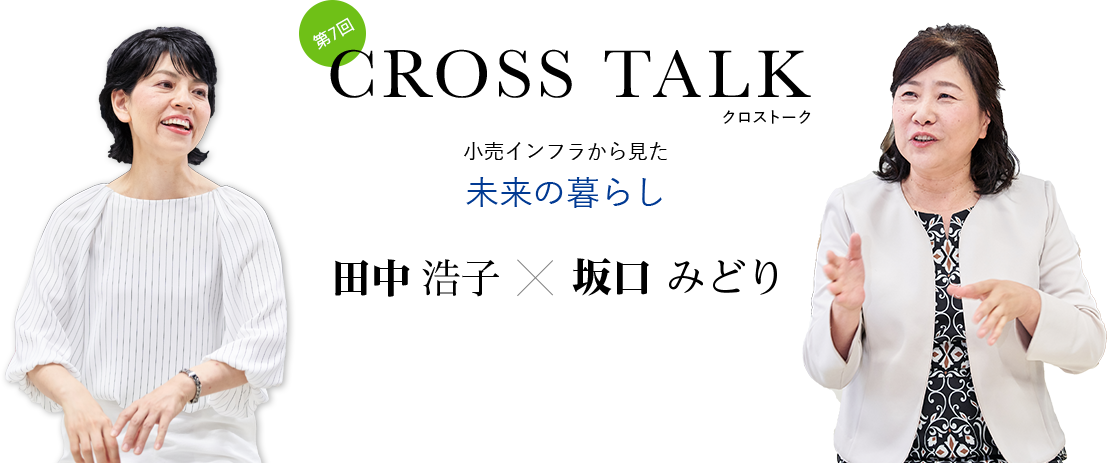出会いは、ひとめぼれ
-
みどりさんに出会ったのは、12年前。管理栄養士を探しているということで、当時、四条にあったうちの事務所に来てくれた。
-
そうですね。お仕事のパートナーとしての管理栄養士さんを探してた。当時の管理栄養士さんのイメージって、「あれしちゃダメよ、これしちゃダメよ、こうしないといけないですよ、ああしないといけないですよ」という、「なければならない」という形のお話をされるというイメージがつよかったんですよね。もうちょっと普段のくらしの中でいろんなアドバイスしてくれるような人を求めていて…。自分で料理できない時だってあるじゃないですか。お酒のんだり、二日酔いしたり、そういうこともひっくるめて、相談に乗ったり、情報を発信したりしていただける、そういう管理栄養士さんを探してたんです。それで縁あって、紹介してもらったのが最初。会った途端にひとめぼれでしたね。この人とやったら一緒にお仕事して楽しいわ、って、思いました。お互い会社のこともよくしらないまま(笑)、その場で具体的な仕事の話をしたこと、憶えてます。
-
そうですね。そこからが始まりで、クロストークの2回目で登場した小椋さん、東山さんにお仕事をいただいたんですよね。
-
生協のカタログで、食生活提案をしていただきました。私は、「管理栄養士界の吉本」って名乗っていたのにも、ちょっと共鳴して。関西人にとって、吉本って日常生活の中に笑いやエンターテインメントをいろんなカテゴリーの笑いをセレクトして届けてくれる存在。食提案についても、日常生活の中で楽しいと思っていただける、笑顔になっていただける届け方をしたいと思っていたので。
-
あの頃、「どんな会社ですか?」とよく言われていたんですよ。それで、「管理栄養士の吉本興業みたいなものです。管理栄養士をビジネスマネジメントしてます」と言ってたんですよね。講演が得意な人もいれば、エッセイ書くことやレシピを作ることが得意な人もいて、いろいろなタイプの管理栄養士がいるので、彼女たちをビジネスマネジメントするということで吉本興業みたい!と話してました。


仕事の原点は、店長時代
-
みどりさんは、今、カタログなどの制作を行なう会社の代表ですが、そもそも 、どういった経緯でこの業界に?もともと和歌山の出身で、大学から京都なんですよね。
-
そうです。大学は文学部でした。卒業後のイメージを明確にもっていたわけではないですが、少なくても小売業で仕事するなんて、当時の私の中には全くなかったですね。
-
ええ!? では、いったい、なぜ?
-
大学でボランティアサークルに入ったのがきっかけで、卒業後、もっとちゃんと福祉の勉強をしたくて、通信の大学で勉強しながら、大学生協でアルバイトしていました。当初は、福祉施設等で働きたいという気持ちが強かったのですが、これからは地域社会がどう機能し、お互いに貢献していくのかが大事になってくるんじゃないかなとも感じていましたし。そういうことに関わるのもいいなとも思っていました。そんな折、「生活協同組合というのは、これから10年先、20年先、30年先、地域社会にどういう貢献ができるのかを考えていける組織だから、坂口さんにぴったりじゃないか?」と上司に言われて。なるほど、と思って就職した、というわけです。
-
入ってみてどうでした?
-
最初の3年間はチェッカーさん。わかります?レジの担当です。当時は今のようにスキャナーで読み取るレジではなくて、「456円」とか言いながらキーボードを打ってました。これの何が地域貢献福祉やねんって(笑)、当時は思ってましたね。その後、チェッカーから副店長、バイヤー、商品開発担当をして、また現場に戻って店長してカタログ制作して…と。いろいろな経験を繰り返してるうちに、就職当初の「騙された!」が、「あ、もしかしたら…」となりました。
-
なるほど。なるほど。
-
基本的に小売業は地域の方たちのくらしに貢献するものだと思うんですよ。社会的役割もたくさん持ってる。当時はまだ、そういう考えは流通業界には少なかったかもしれません。でも、生協はそのことを基本としている組織なんですね。それが見えてきて、あ、何かできるかも、と思うようになりましたね。
-
インパクトの強かった、記憶に残る仕事、あります?
-
やっぱり店長時代と商品開発かな。
-
店長時代のエピソードってあります?
-
最初は、移転改装を控えている約80坪の小さなお店に店長で着任をしました。一時期、生協は「1学区にひとつお店を作りましょう。身近にある小さなお店を作っていきましょう。」という取り組みをしていたんです。
-
それ何年ぐらいの話ですか?
-
「1学区にひとつのお店を」という取り組みは、1980年代前半でしょうか…。店長になったのは1992年頃。1日3回ぐらい来てくれる人がいたんですよ。
-
今でいうコンビニ状態ですね、家に冷蔵庫のない。
-
そうそう。「店長、また来たよー」ってお店に入ってきてくれる。今だにその時の状況が思い浮かびますね。移転改装して大きい店になったら、そんなに頻繁に来てくれないかもと思ったけど、やっぱり毎日来てくれる。「店長、キレイになったねー」って言いながら…。あの時の状況と感覚が今でも忘れられませんね。
-
そうなんですねぇ。
-
店を改装したのが12月。翌月の1月に阪神大震災が起こりました。
-
1995年。
-
店は、結構揺れが大きかった地域にあったんです。当時まだ和式の便器だったんですけど、半分にパカーンって割れるぐらいの被害でした。店に飛んで行ったら、もう、ぐちゃぐちゃ…。で、パートさんが出勤して来るんですよ、自分の家もぐちゃぐちゃやのに。「店をちゃんとあけてあげないと、近所の人が困るから」って。この話になったら、今でも涙出るんですけど…。店長を経験できたこと、パートさんたちがすごく支えてくれたこと、利用する人がほんまに自分の家の冷蔵庫みたいに使ってくれたことが私の中で大きな位置を占めてますね。
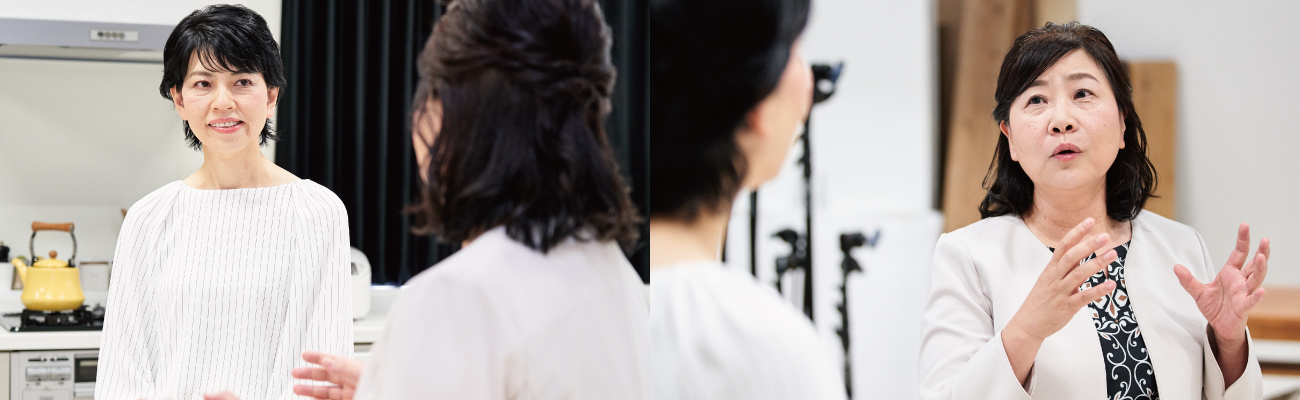

成功も失敗も経験した商品開発
-
商品開発はいかがでした?
-
それまで商品開発は、バイヤーが兼ねてたんですね。でも、独自商品の開発に注目が集まるという時代背景もあって、商品開発担当をおくことになりました。これがねぇ、いろいろやらかしました。早すぎたり、ずれてたり。
-
(笑)早すぎた?
-
自分も周りも働いてる子たちが大半だったから、手軽に作ることができて、おいしいものがほしいと思って、冷凍ピラフを開発しようとしたんですね。これは最初、一緒に開発を進めていただいている利用者に反対されました。「世の中そうだからと言って、なんでも簡単な方をすすめるというのはどうなのか? 生協で開発する意味があるのか?」というようなことを言われましたね。でも、どうしても開発したくて、地元で生産されている米を使いました。意味をつけたんですね。
-
ええーー!
-
地元のお米を使って、地元にある冷凍工場で作ってもらったんですよ。「どう?これで!」みたいな。そしたら、承認いただいて、結果ヒット商品。これはちょいズレしたけれど、結果、成功した事例です。
-
ということは失敗も?
-
いっぱい(笑) バイヤー時代に業務用の冷凍目玉焼きをみつけたんです。朝、目玉焼き作るの、面倒くさいじゃないですか。「ボイルするだけやし、これ、ええやん!」と思って…。
-
うーん、どうかなぁ、どっちが面倒かなぁ?
-
やっぱりそう思います?利用する人たちからも、「何?あの手抜きの目玉焼きは。男の人が考えてるから、こんなもんが企画されるんや」と(笑)。これも印象に残ってますねぇ。利用者の欲しいもの、必要なものではなくて、自分勝手な感覚で進めていたから、当然、失敗になりますよね。
-
なるほど。生協は私も利用してました。最初は店舗利用で、その後、班配達に入ったんです、近所の方との距離が近くなるかなぁと思って。これは、本当に良かった。週に1回、定期的に近所の方とコミュニケーションが取れました。私は、生まれてからいままでずっと自家用車なしの生活なので、食品以外の大きいものも含めて全部配達してくれることがすごくありがたかったですね。冷凍ミンチは頻繁に買ってました。ミンチって、すぐ使わなくちゃいけないけど、パラパラの状態で冷凍してあって。すごく使いやすくて、あれが、私の中ではヒット商品。
-
パラパラミンチは、今でもヒット商品。変化していくニーズにもきちっと合ってるんですね。
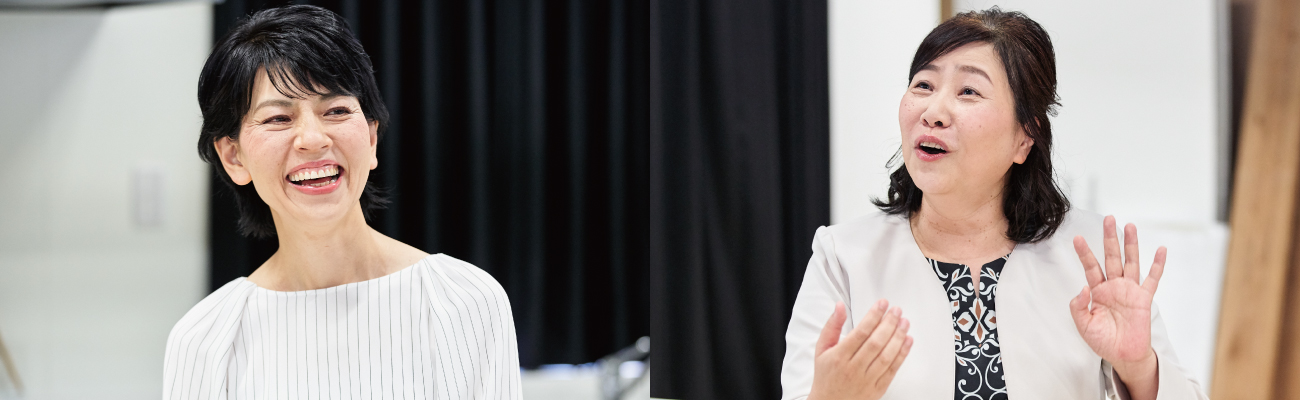

小売業で学んだ3つのM
-
みどりさん、その頃の経験で何を学びました?
-
マネジメントとマーケティングとマーチャンダイジングは、小売業にいる中で学びましたね。これは、今の仕事にも生かされてます。
-
マネジメントって概念が広いでしょう。実践で学んだマネジメントってどういうあたりです?
-
シンプルに組織目標の設定と達成。大切なのは、人と物と金、それと社会。マーケティングもそうですよね。どれだけその時代の暮らし方を見ることができているか。マーチャンダイジングも、その地域の方たちが、何を欲しているかっていうところまで考えないと商品を揃えられないし。会社で置き換えたら、社員一人ひとりのことをどれだけわかってるのかな、というのが大切。クライアントは、どうなのか。クライアントのその先にいる人たちはどうなのか。 結局、人と社会に行き着く気がします。
-
小売業でのマネジメントって、何かひとつの課題が生じた際、全体としての課題を解決するためには、人の問題も含めた全体のマネジメントをするという感じでしたか?
-
そうですね。
-
人的マネジメントって最近よく言われるけど、スタッフのマネジメントって大変ですよね。
-
そうね。やっぱり働いている一人ひとりがどういう気持ちで働いているのかということと、自分たちがこの店をどうしたいのかということで一致する点がないとモノもコトも動かないですね。だから、言われて動く、ではなくって、自ら動いてもらえるようにどうするかを大事にしてました。私、初の女性店長だったんですよ。
-
おおーー。初めて、だったんですか!
-
やっぱり当時は、ハードだったんですよね。力仕事もあるしね。店長になった当初は、「ん?大丈夫?」って思われてたのが、途中から「応援してあげよう」に変わってくれた。そういう変化を生むのもマネジメントのひとつなのかなとも思いますね。


生活者視点を忘れない
-
ずっと生活者視点で事業を考えられてきたというのが、みどりさんに対する私の最初の印象なんですけども。生活者って、お悩み事がいっぱいあるでしょ。「もっと良くなったらいいのに」と思うこともあるし、自分では気がついてないこともあります。そこを掘り下げたり、見つけたりしてますよね。
-
そうありたい。「そうやねん!そこやねん!」と思ってもらえたら、「よっしゃーっ!」ていう感じ。
-
自分でもわかってない、気づいてないニーズに、提供側が「これどう?」と示すと、「おっ!これか」と反応が来る。ネットで検索してるだけではわからないですよね。ネットで検索したり、「どうですか?」って聞いてるだけではわからないことってありますよね。
-
わかんない。「どうですか?」「何がほしいですか?」と聞いて出てくるものは、すでにあるものでしょう。ないものを探してあげないと。汲み取る側がどれだけ汲み取れるのか、ですよね。
-
いわゆるマーケティング力だと思うけど、汲み取る力って、どうやったら上がるんですか?どうやったらお客様の欲しいものがわかるんですか?
-
うーん、いろんなことの積み重ねですかねぇ。まあ、まずは現場。お客さんを見てなかったら、お客さんのことはわからない、というのはある。
-
それは、買うところ?買う場面を見ている?
-
買う場面だけじゃなくて、暮らしそのものかなぁ。買う場面を見て、食事をされてるシーンとか家族のこととかストーリーを思い描いている。それと、自分自身ですよね。どれだけインプットできてるか、もあると思うし。関係のないことはない、と思うようにしてるんですよ、私。
-
関係がないことはない。
-
食の仕事してるから、食以外のことは関係ないとは思わないんですよ。それだけは、気をつけてるんです。
-
生活って全部ですもんね。区切りがない。こういう人たちがこういうことに困ってるんじゃないかとわかった時に、それに対する解決法、解決案は、自分の中から、「うんっ、これ!」って感じで湧き出てくるわけですか?
-
そう。「うんっ!」と出てくる(笑)。出てくるけど、具体化しようと動き出すと、そこには経営やいろんなことが付きまとってくるでしょう。だから、それを加味して、私は今BtoB、すなわち企業対企業の仕事をしています。直接的に生活者の方に何かをできるということではないんです。でも、クライアントを通じてその先にいる生活者に届けたいという気持ちで向き合ってますね。その先を見ているというのは、ずっと地域の生活を見てきたというのが大きい。すごく今の仕事には大きいですね。
-
これまでの仕事での積み上げがあってこそ、気づく力も提案をする力も大きくなってきたっていうことですよね。


すべてはジブンゴト
-
企画、宣伝、品揃え、媒体制作といった宅配事業の組み立てもしてたでしょう。その中でここは外せない、と思ったことは何ですか?
-
宅配事業の中で?
-
私たち生活者には、コンビニやスーパーなど食品を得る場所もご飯を食べる店も選べますよね。その中で「やっぱり生協よね、それも生協の宅配よね」と思うところがないと生協の宅配はしない。どこに強みを打ち出していたのかな?と。
-
店舗とカタログの違いって、やっぱり商品の種類なんですよ。いくら物流が開発整備されて増えてきても、小さな店舗に満たない。では何をすべきかというと、私は編集作業やと思うんです。こういう暮らし方がありますよ、その暮らし方をこの商品がサポートしますよ、という。
-
あなたの暮らしなら、こういう食生活してみませんか?みたいな提案ですか。
-
そう、それ。生協を出た今の方が見えてきている気がしますね。自分一人だと自分の視点だけやけど、いろんな方たちに入ってもらってチームができると、視点も多角的になるし、それぞれ専門分野があって脳がいくつもあることになる。内部で発信するのではなく、外部の一歩引いてみた地点で、こうじゃないですか?と提案することができるようになってきました。
-
食べることというお題は変わらないけど、見るポジションが変わってきた、と。
-
お客様に近いところにいた方がいろいろできると思っていたけど、一歩引いた場所の方が全体を見渡せるようになりました。結局、みんな食べないと生きていけない。みんな自分ごとなんですよね。世の中の人の自分ごとでもあるし、自分の自分ごとでもある、と捉えるようになりましたね。


食の現場で働いているのに求めるものがない!?
-
忙しい時、ご自身の食生活は、いい感じでした?
-
全然良くないですよ(笑)。全然良くない。ほんとひどかった。
-
食べものいっぱいあるのにね、周りに。いくらでも買えるのに。食べものが手に入りやすい場所にいるか、どうかじゃない。これ、食料品アクセスの問題だけではないって話ですよね。
-
うーん、すぐ近くにはあるんだけど、私の動線にはなかったって心境ですよね。家と店、家と事務所を往復する毎日で、この動線の中に、私の食はなかったですねぇ。家と店の間に、ひと手間でできる食材を買えるところがあったら、そこで買ってたかも…(笑)。当時の私は、ほんとに買って帰ってボイルやチンで食べられるものが欲しかったから。そういうのがきちんと全部揃ってるところ、「今日はコレ食べなはれ」っていう店や商品があれば、うれしかった。
-
わかる、わかる!私、大学院生の頃、2005年ぐらいかな。そんなことをよく同級生と喋ってたんですよ。すごく印象に残っているのが、忙しいから中食は使いたいんだけれど、売ってるものが変わり映えしないって話。好きな中食の店はあるのに、毎日毎日一緒のものを売っているから食事が成り立たない、買いたいと思ってるのに買う店がない、と。店に行ったら「はい、今日のお宅の食事」って毎日渡してくれたら買って帰るのにって言ってました。でも、そういう栄養士を私たち育ててないし、そういう状態を作ってないよね、ニーズあるんじゃない?でもそういうサービスないよね、って。
-
本当に暮らしかたで動線って変わってきますよね。退職して、会社に行かなくなったら、それはそれで暮らしは変わるだろうなぁと。暮らしが変わっても、わざわざ行かなくても良いところに買いたいものがある店が欲しいなという願望は持っていますね。


2050年の食の、変わる部分と変わらない部分
-
今年から、立命館大学で客員研究員もしていただいてるんだけれども。提供側にいるみどりさんは、30年後、2050年の食ってどうなってると思います?
-
正直言って、そんなに変わってないような気がするの。
-
食べるもの自体?食卓に上がるものは変わってない。
-
食べるものは変わってない気がする。でも、今の90歳の方たちと、私たちが90歳になった時の食シーンは、もしかしたら変わってる。違うんじゃないか、と思う。
-
違うもの、食べてる?
-
同じものなんだけど、食べかたや食べる場所が変化するかな。ちょっと希望も入ってるんだけれども。
-
どんな感じでありたい?
-
誰かいてほしい。でも、一人でもいたい。両方が成り立って欲しい。
-
この前、同じような質問を大学でやった時に、学生が「共に」、って書いて共食がいいって。
-
そうそう。そういうインフラ整備ができてくれると嬉しい。
-
なるほど、なるほど。食べるものはあんまり変わんないけど、ってとこよね。
-
変わると思う?
-
変わらないと思う。だって30年前振り返っても食卓の上は変わってない。平成30年間で変わったのは、その後ろにある、つなぐ仕組みですよね。提供する仕組みは変わってきたと思うんです。昭和の頃は市場に行って八百屋さんや魚屋さんで買っていたのが、スーパーで買うようになって、コンビニや宅配も登場した。買うところが変わってきた。買うところの後ろにある仕組みは変わってきているけど、結局食卓に乗るのは同じ食べもの。
-
物流やシステムは、多分ものすごく変わると思うけど、暮らしてる私たちの目の前に出てくる食材が変わるかっていうと変わらないし、食べ方が変わるかっていうと、そんなに変わってない気がしますよね。
-
そうですね、仕組みやシステム、そしてインフラや決済も変わりますよね。そんな状況で、私たちが今やろうとしていることは、30年後を見越してどうなるんだろう、という予測ではなくて、積極的に創っていきたいということ。今のポジションなら、いろんなところで話し合える、いろんなところに発信する力もあるし、影響力があるところにいると思うんですよね。だから、やっぱりこれからの仕組みはこうありたいよね、こう作っていきませんか、と働きかけて、変えていかないと。30年後に、どうして30年前に私たちは行動しなかったんだろう、と後悔はしたくない。タラレバは絶対ないようにしておきたい。30年あったら、食の方法ももうちょっと変えられたはずなのに、「あのとき手を打たなかったのでこんな状態になっちゃったね」とはしたくないですよね。ここは多分、この研究会でみんな思ってるところ。
-
さっきの話じゃないけど、すでにあるものしか想像できないので、具体的に描けるものをきちんと提案していかないと、っていうのがある。生活者のことを考えるけど、その人たちに実際にサービスを提供する流通の人たちにどう働きかけるか。アクションを起こしていく仕事がしたいですね。ライフワークっていうか。自分の将来も考えてね。日常の、ことに「食」を考えると、やっぱり売っている店が大事。店がないところは作ってあげないといけないと思うし。それは大手のスーパーも地域のスーパーも生協などの宅配もコンビニも、みんなで考えないと。何を次に提供していくのか、サービスのコンテンツを考えていかないとあかんなという思いがあります。


今あるものを少しずつ変えていきたい
-
人は、食品スーパーや食品小売業に、単にモノを買いに行ってるというだけじゃない。その考えは、多分、私とみどりさんの共通するところだと思うんだけれども。では、何を買いに行ってるんだろうか…。食品を買うだけだったら、宅配サービスもあるし、ネットスーパーもあるでしょう。20年30年経った時の食品小売業に、人は何を求めているか?あるいは今、何を求めてそこに行っているのか?
-
そこ、考えないといけないですね。
-
30年前と大きく変わってきたのは、たとえばイートインスペース。昔はなかったでしょう。お惣菜も充実してきて、それを店の一角で食べるようになった。今問題になっているプラスチック製の容器に入ったお惣菜をそのまま食べている。持って帰らなくて、あえて、そこで食べているって…何でしょうね?外食することもできるし、食べる選択肢はあるのに、中食を買って、それを持ち帰らずに店内で食べる。そこには、何か意味や理由があるってずっと思ってるんですよ。例えば、仕事で外をまわっていて、その移動の途中で買って食べるのはあると思うんだけれども、日常的にイートインスペースで、あそこでごはんを食べるということは、どういうことなんだろう?
-
同じ風景が同じ曜日の同じ時間に見えることってあるよね。食事をされている方たちのところに、ひょいひょいって入っていけるような仕掛けができたら、理由もわかってくるし、そこで食べるという意味合いも変わってくるんじゃないか、と思ったり。イートインスペースが、単なる中で買ったもの、あるいは持ち込んだものを食べるスペースではなくて、コミュニティスペースにしていく。これなら今のインフラで、できそうでしょう?
-
自分で使っても、この部分がもっとこうだったらいいのになって思うところがいっぱいあって。改善点いっぱいありますでしょ?
-
あります、あります。まあ、単純なこと言ったら、イートインスペースをもうちょっと温もりのある空間にしたらだいぶ違うやろな、とか。
-
やっぱり。景色変えたい、ですよねぇ。
-
そうそう。イートインコーナーの景色変えたい。なんかもう…ねえ。
-
楽しそうに見えないんですよね。
-
ちょっと小洒落たものがあるだけで、もう全然雰囲気が違うと思うんですけどねぇ。提供側からの景色は変えていけるだろうなと。
-
そうですね。
-
30年後の食ということで言えば、クロストークの3回めで百武先生が30年後の食の予想をスケッチしてたでしょう。あの30年後に向かって、今から突っ走るのかというと、そうじゃないと思っていて。今ある中で改善をしながら、ちゃんと観察をしながら、話も聞きながら、あのスケッチに向かっていかないといけない。そうなると、もう始めないとアカンと思ってるのね。あんまり大きな投資ではなく、実験を繰り返しながら進んでいくというのが大事かな、と思ってて。つい最近、美容室で喋っているときに、スーパーの話になったんですよ。スーパーって食品があるし、大きなところになると寝具もあるでしょう。これだけ自然災害が起こるご時世だから、公民館や小学校だけを避難所にするんじゃなくて、スーパーが避難所になってもいいやん、みたいな話。公民館の維持や小学校の統廃合という社会背景で、避難所自体が遠いやんという状況もあるんだけれど。
-
災害時の拠点となる。店内にいっぱい食品もあって、特に冷凍食品からどんどん傷んでくるわけだから、それらを使いながら、ってことですよね。
-
うちはすぐ近くに大きなスーパーがあって、そうなってくれるといいよねっていう話をしてたのね。緊急時だけじゃなく、普段から、そういう地域のコミュニティの場所的なことを意図してやれればいいなと思いますね。あと、店内キッチン。なんとかしたいですね〜。
-
あれ、できた頃ってすごい画期的でしたよね?以前はホットプレート上で試食品を焼いてたのが、ちゃんと店内キッチンができて、いい感じになって、すごく嬉しかったのに、なんかだんだん…。もっと使いかたがあるように思えるんですよね。
-
あれをインフラに使えないかな、と。
-
だから、今の設備をガラリと変えなくてもソフトの問題ってことですよね。店内キッチンもそうだし、イートインスペースもそうだし。
-
店内キッチンとイートインコーナーを連動させることもできるでしょ。事業なので成り立たないと継続も発展していかないから、そういう意味では商品を売ることも当然できるはずなので。お客様が喜ぶし、事業的も成り立つと思いますね。移動販売車も、ただ単に商品を売り買いするだけではなくて、そこで生まれるものごとがあると思います。流通業界や小売業界が持っているインフラを使って変えられることって実はたくさんあるんじゃないかと思ってて。まだ未知数ですけど、その発信をしていきたいですね。


買い物をしたら健康になる、を提案
-
私は健康というキーワードを外せないと思っているんですけど、流通業界と連動してない感じがするんですね。
-
提案しっぱなし。
-
バラバラって感じ。保健所も流通も提案するけど、横串が刺さってないな、と思いますね。大学の研究という切り口からつなぐことができるんじゃないか、と思っているんですけど。
-
理想を言うなら、先々でもいいけど、普通にお買い物をしてると、「ハイ田中さん」「ハイ坂口さん」と、健康と連動している商品提案をしてもらえるとこんな嬉しいことはないと。特に、宅配は編集できるんで、そういう編集提案をすることができるんじゃないかな、と。しかもお家まで運んでくれるっていいと思いません?
-
お買い物と健康の連動の話って、10年ぐらい前からしてません?私たち。ずっと言ってるけど、そろそろ時代に乗ってきてます?
-
そうそう、言ってるだけじゃなくて、購入量と家族構成をもとにした計算ロジックを組み立てて、栄養バランスの状況とアドバイスを提供できる仕組みをつくりましたよね。システム設計までしたもの。買い物して、それを食することでバランスがとれるという仕組みは生活者にとっては絶対に嬉しいと思う。
-
そこが、なかなか流通業と結びついてないんですよね。
-
流通業と連動できれば、いろいろなパターンでの提案ができるだろうし、事業貢献もできると私は今でも思っていて。健康は外せないテーマだしね。
-
1回めのクロストークでも話したナッジ=仕掛けを作って、気がつけば健康でした、というのをやっていきたいんです。
-
10年温めてきた仕組みを未来にむけての事業として成り立つように組み立て直したいですね。食べ方を提案する田中メソッドの考え方も取り込んでブラッシュアップさせてね。 時代に乗ってきてますよ。
-
そうですね。やってみたい。
-
買い物する場所と、買い物する人を、きちんと結びつけて、そこにキーワードである健康が含まれてる。健康を意識することなく、買い物をしても、健康と買い物が結びついているという状況ができればいいなぁ、という気がしますね。食を中心にしたコミュニティづくりも、コミュニティそのものが事業として成り立つという状況に持っていければ、持続できる。
-
いわゆる社会的課題と、事業としてちゃんと成り立つという、ここの考え方が一番重要ですね。



坂口 みどり
株式会社キュービック・アイ 代表取締役社長。メディアパークホールディングス株式会社取締役。株式会社ルーフ取締役。
立命館大学BKC社系研究機構 客員研究員。
大学卒業後、1982年に生活協同組合に入協。店舗・宅配の現場や商品開発等の職種を経験し2008年に退職後、現在の会社に入社。2016年に代表に就任。ライター:宮前 晶子
カメラマン:田口 剛
ヘアメイク:石田 咲苗